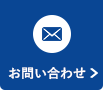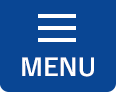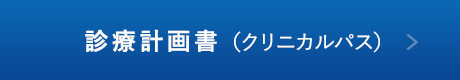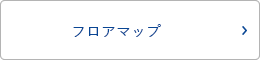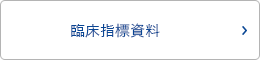泌尿器科
トピックス
・2024年3月よりMRI融合前立腺針生検を開始しました。
・2023年10月より当院の手術支援ロボットがdaVinci SiからdaVinci Xiに更新されました。
・2023年5月よりサイズの大きな腎結石に対して経皮経尿道併用結石破砕術(ECIRS)を開始しました。
・2022年7月より腎盂尿管移行部狭窄に対してロボット支援腎盂形成術を導入しました。
・2022年4月より前立腺肥大症に対してツリウムレーザーを照射して前立腺組織を蒸散し縮小させる経尿道的ツリウムレーザー
前立腺蒸散術(ThuVAP)を開始しました。
・2023年10月より当院の手術支援ロボットがdaVinci SiからdaVinci Xiに更新されました。
・2023年5月よりサイズの大きな腎結石に対して経皮経尿道併用結石破砕術(ECIRS)を開始しました。
・2022年7月より腎盂尿管移行部狭窄に対してロボット支援腎盂形成術を導入しました。
・2022年4月より前立腺肥大症に対してツリウムレーザーを照射して前立腺組織を蒸散し縮小させる経尿道的ツリウムレーザー
前立腺蒸散術(ThuVAP)を開始しました。
泌尿器科の特色
泌尿器科悪性腫瘍の治療をはじめ、尿路結石症、排尿障害(前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱、尿道狭窄症など)、尿路感染症、女性泌尿器科疾患など泌尿器科疾患一般を幅広く診療対象としています。
各分野に精通した医師を中心に、週5回のカンファレンスを行って治療方針を統一し、どの医師でも一貫した方針で治療を提供しています。医師から患者・家族に十分な情報提供を行った上で、患者・家族の希望を尊重し、治療方針を一緒に考えるように心掛けています(”Shared dicision making“)。
当院では2013年7月に、静岡県で3番目、静岡県中部で最初に手術支援ロボットを導入しました。泌尿器科は導入当初から前立腺癌に対する前立腺全摘術を開始し、その後の保険適応の拡大とともに以下のようなさまざまなロボット支援手術を行っています。
主任科長が日本泌尿器科学会と日本泌尿器内視鏡学会の認定するロボット支援手術プロクター(手術指導医)であり、泌尿器ロボット手術認定(certificate取得者)が計4名在籍しています。
各分野に精通した医師を中心に、週5回のカンファレンスを行って治療方針を統一し、どの医師でも一貫した方針で治療を提供しています。医師から患者・家族に十分な情報提供を行った上で、患者・家族の希望を尊重し、治療方針を一緒に考えるように心掛けています(”Shared dicision making“)。
当院では2013年7月に、静岡県で3番目、静岡県中部で最初に手術支援ロボットを導入しました。泌尿器科は導入当初から前立腺癌に対する前立腺全摘術を開始し、その後の保険適応の拡大とともに以下のようなさまざまなロボット支援手術を行っています。
主任科長が日本泌尿器科学会と日本泌尿器内視鏡学会の認定するロボット支援手術プロクター(手術指導医)であり、泌尿器ロボット手術認定(certificate取得者)が計4名在籍しています。
当科のロボット手術実績
2013年7月~2025年3月
| 対象疾患 | 手術術式 | 導入 | 通算件数 |
| 前立腺癌 | 前立腺全摘術 | 2013 | 564 |
| 腎癌 | 腎部分切除術 | 2017 | 106 |
| 膀胱癌 | 膀胱全摘術 | 2019 | 69 |
| 腎盂尿管移行部狭窄 | 腎盂形成術 | 2022 | 8 |
当科のロボット手術実績については泌尿器科ロボット支援手術のページもご参照ください。

腎癌
腎臓内にとどまっている早期癌であれば、手術による切除が原則です。癌の大きさや位置により、可能な限り腎臓の正常部分を残す腎部分切除術を行います。部分切除が難しい場合には、腎臓全体を摘出します。部分切除はロボット支援手術で、全摘は腹腔鏡手術で行っています。大静脈内に進展していたり周囲臓器に直接浸潤している進行腎癌に対しては、抗癌剤(分子標的薬)や開腹手術を組み合わせていますが、最近では分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤など新たな治療手段が続々と登場しており、転移があったり根治切除困難な進行腎癌でも、長期の延命やQOL(生活の質)維持が可能となってきています。
腎癌の最近の手術方法についてはこちら
腎癌の最近の手術方法についてはこちら
腎盂尿管癌(上部尿路上皮癌)
原則として、腎臓と尿管を摘出する腎尿管全摘術を行います。ほぼ全例を腹腔鏡にて行います。悪性度の低い下部尿管癌などでは、尿管部分切除術を行う場合もあります。進行してしまっていて転移がすでにある腎盂尿管癌に対しては、ゲムシタビンシスプラチン療法などの抗癌剤治療を行い、QOL(生活の質)をできるだけ維持し延命をはかるようにしています。尿路上皮癌に対しても免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬が近年登場し、転移を有する尿路上皮癌でも長期の延命やQOL(生活の質)維持に寄与しています。さらに、特定の遺伝子変異を持つ尿路上皮癌に効果のある抗癌剤も登場しました。
膀胱癌
早期であれば内視鏡手術(経尿道的手術)で治癒させることができます。内視鏡切除ができない浸潤性膀胱癌に対して、従来では開腹での根治的膀胱全摘術を行ってきましたが、長時間の開腹手術で侵襲が大きかったことから、条件さえ合えば腹腔鏡での手術を行うようにしました。2019年5月からはロボット支援での腹腔鏡下膀胱全摘術も導入し、以後のほぼ全例をロボット支援で行っています。膀胱を切除してしまうと尿の出口を新たに作成する尿路変更術が必要ですが、当院では回腸利用新膀胱、回腸導管、尿管皮膚瘻の3つの尿路変更について詳しく説明した上で、患者さんの状態や希望に応じてそのどれかを選択するようにしています。術後早期回復プログラム(ERAS)の導入により、膀胱全摘の際の入院期間が2週間程度に短縮しました。
転移のある膀胱癌に対して、腎盂尿管癌と同様に、抗癌化学療法(ゲムシタビンシスプラチン療法や免疫チェックポイント阻害剤、分子標的薬など)を行い、QOL(生活の質)をできるだけ維持しながら延命をはかるようにしています。特定の遺伝子変異を持つ尿路上皮癌に効果のある抗癌剤も登場しました。転移がない膀胱癌でも、根治性を高めるために手術前後に抗癌化学療法を行うこともあります。
転移のある膀胱癌に対して、腎盂尿管癌と同様に、抗癌化学療法(ゲムシタビンシスプラチン療法や免疫チェックポイント阻害剤、分子標的薬など)を行い、QOL(生活の質)をできるだけ維持しながら延命をはかるようにしています。特定の遺伝子変異を持つ尿路上皮癌に効果のある抗癌剤も登場しました。転移がない膀胱癌でも、根治性を高めるために手術前後に抗癌化学療法を行うこともあります。
前立腺癌
PSA値が高い方を対象に、直腸診、経直腸エコー、前立腺MRIなどを行い、前立腺癌が疑われる場合に、肛門からエコーガイドで前立腺を穿刺し組織を採取する経直腸前立腺針生検を行います。ほとんどの方が外来通院で無麻酔での経直腸前立腺針生検を選択されますが、希望に応じて短期入院、麻酔での生検も可能です。経直腸前立腺針生検で癌が見つからず、それでもPSAが上昇する場合、麻酔をかけて会陰部から穿刺する経会陰前立腺針生検を併用しています。前立腺癌が見つかると、CT、骨シンチグラフィーなどで癌の広がりを確認し、適切な治療方法を検討していきます。
早期癌には根治手術、根治的外照射、進行癌にはホルモン療法などが選択枝となります。当院で施行可能な治療だけでなく、他院で行われている治療(粒子線治療、小線源療法)などにも言及しながら、患者さんの希望に応じた治療を提供していきます。
早期前立腺癌に対して、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RALP)を2013年7月に開始しました。年間約60件のRALPを行っており、出血量が少なく、低侵襲で質の高い機能温存が可能となりました。周囲進展やリンパ節転移が予測される患者さんには、拡大切除や拡大骨盤リンパ節郭清などを併用し、根治率を高めるよう工夫しています。術後再発と関連する「切除断端陽性率」が他院より低い(全国平均が10-20%のところ、当院では5%以下)のが当院でのRALPの特徴です。
根治的外照射については、放射線治療科と連携し、強度変調放射線治療(IMRT)/強度変調回転照射(VMAT)も多数行っています。通常分割法70~78Gy/35~39回のほか、一回の照射量を増やして照射回数を減らす「寡分割照射」も導入しており、18~20回の照射で治療が完了します。前立腺に限局した早期癌だけでなく、骨盤リンパ節転移を伴うD1期や、全身治療で転移巣が消失またはコントロールがついた際の前立腺局所照射も状況次第では適応となります。外照射の多くがホルモン療法を併用します。
転移のある進行前立腺癌にはホルモン療法を行います。新規ホルモン療法剤イクスタンジ、ザイティガ、アーリーダ、ニュベクオなどが発売され、去勢抵抗性前立腺癌の患者さんの余命延長に役立っています。ホルモン療法後に再燃した場合には、ドセタキセル、カバジタキセルなどの抗癌剤治療を行います。特定の遺伝子異常を持つ前立腺癌に効果のある抗癌剤(リムパーザ、ターゼナ)も登場しています。
前立腺癌の治療方法についてはこちら
MRI融合前立腺生検についてはこちら
早期癌には根治手術、根治的外照射、進行癌にはホルモン療法などが選択枝となります。当院で施行可能な治療だけでなく、他院で行われている治療(粒子線治療、小線源療法)などにも言及しながら、患者さんの希望に応じた治療を提供していきます。
早期前立腺癌に対して、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術(RALP)を2013年7月に開始しました。年間約60件のRALPを行っており、出血量が少なく、低侵襲で質の高い機能温存が可能となりました。周囲進展やリンパ節転移が予測される患者さんには、拡大切除や拡大骨盤リンパ節郭清などを併用し、根治率を高めるよう工夫しています。術後再発と関連する「切除断端陽性率」が他院より低い(全国平均が10-20%のところ、当院では5%以下)のが当院でのRALPの特徴です。
根治的外照射については、放射線治療科と連携し、強度変調放射線治療(IMRT)/強度変調回転照射(VMAT)も多数行っています。通常分割法70~78Gy/35~39回のほか、一回の照射量を増やして照射回数を減らす「寡分割照射」も導入しており、18~20回の照射で治療が完了します。前立腺に限局した早期癌だけでなく、骨盤リンパ節転移を伴うD1期や、全身治療で転移巣が消失またはコントロールがついた際の前立腺局所照射も状況次第では適応となります。外照射の多くがホルモン療法を併用します。
転移のある進行前立腺癌にはホルモン療法を行います。新規ホルモン療法剤イクスタンジ、ザイティガ、アーリーダ、ニュベクオなどが発売され、去勢抵抗性前立腺癌の患者さんの余命延長に役立っています。ホルモン療法後に再燃した場合には、ドセタキセル、カバジタキセルなどの抗癌剤治療を行います。特定の遺伝子異常を持つ前立腺癌に効果のある抗癌剤(リムパーザ、ターゼナ)も登場しています。
前立腺癌の治療方法についてはこちら
MRI融合前立腺生検についてはこちら
その他の泌尿器科領域悪性腫瘍
精巣腫瘍(セミノーマ、非セミノーマ)に対する高位精巣摘除術、後腹膜リンパ節郭清術、抗癌化学療法(BEP、VIP、TIPなど)、陰茎癌に対する陰茎部分切除術、陰茎全摘術、鼠径リンパ節郭清術、抗癌化学療法などを行っています。
副腎腫瘍
サイズが大きく増大傾向があり癌が疑われる場合、あるいは副腎ホルモン(カテコラミン、アルドステロン、ステロイドホルモン)が過剰に産生されている場合に、摘出術を行います。ほとんどの副腎腫瘍は腹腔鏡で切除できます。他領域の悪性腫瘍が副腎に転移した場合にも、積極的に腹腔鏡切除を行っています。
尿路結石
腎結石、尿管結石に対して、体外衝撃波結石破砕(ESWL)、経尿道的尿管結石砕石除去術(TUL)、経皮的尿路結石除去術(PNL)などが可能です。
2023年5月より、サイズの大きな腎結石に対してTULとPNLを同時に並行して行い、より安全で結石完全除去率の高い術式である経皮経尿道併用結石破砕術(ECIRS)を導入しました。
これらを組み合わせて結石の完全摘除を目指すとともに、投薬や生活指導などで再発予防に務めるようにしています。
尿路結石の診断・治療・予防についてはこちら
2023年5月より、サイズの大きな腎結石に対してTULとPNLを同時に並行して行い、より安全で結石完全除去率の高い術式である経皮経尿道併用結石破砕術(ECIRS)を導入しました。
これらを組み合わせて結石の完全摘除を目指すとともに、投薬や生活指導などで再発予防に務めるようにしています。
尿路結石の診断・治療・予防についてはこちら
前立腺肥大症
α受容体遮断薬(タムスロシン、シロドシンなど)、5α還元酵素阻薬(デュタステリド)、PDE阻害薬(タダラフィル)などを用いた投薬治療を行っています。手術治療が必要な場合、尿道から内視鏡を入れ前立腺を切除または核出する経尿道的手術が一般に行われており、 1週間以内の入院期間で内服治療と比べて迅速な効果が得られます。当院ではツリウムレーザーを照射して前立腺組織を蒸散し縮小させる経尿道的ツリウムレーザー前立腺蒸散術(ThuVAP)を2022年4月より開始しました。レーザーの強い止血力により出血が少なく、抗凝固剤・抗血小板剤を内服中の患者さんでもほとんどの方が中止せず手術をすることができ、手術前後の血栓症の発症リスクが減少します。
その他の領域
過活動膀胱、神経因性膀胱の患者さんが多数来院します。QOL(生活の質)を重視し、生活指導や投薬を行います。間質性膀胱炎に対して、投薬で改善しない場合に、膀胱水圧拡張術を行っています。
腹圧性尿失禁が骨盤底筋体操指導や投薬で改善しない場合に、尿道をメッシュテープで支えるTOT(TransObuturator Tape)を行っています。女性性器脱に対して、メッシュを膣壁に埋め込んで支えるTVM(Tension-free Vaginal Tape)を泌尿器科にて行っており、またロボット支援仙骨膣固定術を婦人科で行っています。
2022年7月より腎盂尿管移行部狭窄症に対してロボット支援腎盂形成術を導入しました。
腹圧性尿失禁が骨盤底筋体操指導や投薬で改善しない場合に、尿道をメッシュテープで支えるTOT(TransObuturator Tape)を行っています。女性性器脱に対して、メッシュを膣壁に埋め込んで支えるTVM(Tension-free Vaginal Tape)を泌尿器科にて行っており、またロボット支援仙骨膣固定術を婦人科で行っています。
2022年7月より腎盂尿管移行部狭窄症に対してロボット支援腎盂形成術を導入しました。
外来
※午後にレントゲン検査、前立腺生検、外来手術、ESWLによる砕石術、面談を行っています(完全予約制)
※第2、第4火曜日に皮膚排泄ケア認定看護師(WOCナース)によるストーマ外来(スキンケア外来)を行っています(完全予約制)
※第2、第4火曜日に皮膚排泄ケア認定看護師(WOCナース)によるストーマ外来(スキンケア外来)を行っています(完全予約制)